
| 配信サービス | 配信状況 | 無料期間と料金 | |
|---|---|---|---|
 | レンタル, 購入 | 初回30日間無料 600円(税込) | |
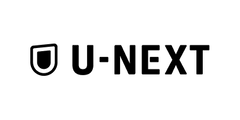 | レンタル | 初回31日間無料 2,189円(税込) | |
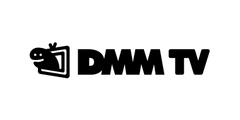 | レンタル | 初回14日間無料 550円(税込) | |
 | レンタル, 購入 | 初回1ヶ月間無料 1540円(税込) | |
 | レンタル | なし 1,100円(税込) |

Prime Videoで、『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』はレンタル配信中です。
| 月額料金 | 無料期間 | 見放題作品数 | ダウンロード | 同時再生可能端末数 | ポイント付与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600円(税込) | 初回30日間無料 | 13,000作品以上 | 可能 | 3端末 | - |
Prime Video トップページから、30日間無料体験のバナーを押します。

「30日間の無料体験をはじめる」ボタンを押します。

Amazonのアカウントをお持ちの方はログイン、お持ちでない方は「アカウントを作成」を押します。

氏名、携帯電話番号またはメールアドレス、パスワードを入力し、「次に進む」ボタンを押します。

入力した携帯電話番号またはメールアドレス宛に確認コードを受け取ります。

確認コードを入力して「アカウントの作成」ボタンを押します。

無料期間が終了した際の支払い方法としてクレジットカード情報を入力し、「カードを追加」ボタンを押します。支払い方法として携帯決済を選択することもできます。

請求先の住所、電話番号を入力して「この住所を使用」ボタンを押します。

お支払い方法を確認し間違いがなければ「続行」ボタンを押します。

プラン、Eメールアドレス、お支払い方法、請求先住所を最終確認し、「30日の無料体験を開始する」を押します。これでAmazon Prime Videoの登録が完了です。

Prime Video にログインした状態で、トップページからアカウントメニューを開きます。

メニューをスクロールし、アカウントサービスから「お客様の会員資格と定期購読」を選択します。

「プライム会員設定」ボタンを押します。

「プライム会員情報の管理」を押し、メニューを開きます。

メニューから「プライム会員情報」を選択します。

「プライム会員資格を終了する」を選択します。

画面をスクロールし、「特典と会員資格を終了」ボタンを押します。

再び画面をスクロールし、「会員資格を終了する」ボタンを押します。

再び画面をスクロールし、「特典と会員資格を終了」ボタンを押します。

解約手続きが終了すると、プライム会員資格の終了日が表示されます。終了日までは利用を継続できます。


U-NEXTで、『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』はレンタル配信中です。
U-NEXTでは登録時に600pt(無料トライアル)のポイントが付与されるため、ポイントを消費してお得に視聴できます。
| 月額料金 | 無料期間 | 見放題作品数 | ダウンロード | 同時再生可能端末数 | ポイント付与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,189円(税込) | 初回31日間無料 | 320,000作品以上 | 可能 | 4端末 | 600pt(無料トライアル) 付与 |
U-NEXT トップページから、「31日間 無料体験」ボタンを押します。

「今すぐはじめる」ボタンを押します。

カナ氏名、生年月日、性別、メールアドレス、パスワード、電話番号を入力し、「次へ」ボタンを押します。

入力内容を確認し、無料期間が終了した際の決済方法としてクレジットカード情報を入力し「利用開始」ボタンを押します。支払い方法として楽天ペイ、d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払いを選択することもできます。

これでU-NEXTの登録が完了です。続いてファミリーアカウントを追加することもできます。

U-NEXT にログインしている状態で、トップページ左上のメニューボタンを押します。

メニューから「アカウント・契約」を選択します。

「契約内容の確認・解約」を選択します。

「解約手続き」を押します。

画面をスクロールして「次へ」ボタンを押します。

画面をスクロールして、「注意事項に同意する」をチェックし、「解約する」ボタンを押します。

これでU-NEXTの解約手続きが完了です。


DMM TVで、『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』はレンタル配信中です。
DMM TVでは登録時に550ptのポイントが付与されるため、ポイントを消費してお得に視聴できます。
| 月額料金 | 無料期間 | 見放題作品数 | ダウンロード | 同時再生可能端末数 | ポイント付与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550円(税込) | 初回14日間無料 | 15,000作品以上 | 可能 | 1端末 | 550pt 付与 |
DMM TV トップページから、「30日間無料トライアル!」ボタンを押します。

「まずは30日間 無料体験」ボタンを押します。

DMM.comのアカウントをお持ちの方はログイン、お持ちでない方は「新規会員登録」ボタンを押します。

メールアドレスとパスワードを入力し、「認証メールを送信する」ボタンを押します。

受信した「DMM:会員認証メール」の本文にあるURLを開きます。

ページをスクロールし、無料期間が終了した際の支払い方法としてクレジットカード情報を入力し、「次へ」ボタンを押します。支払い方法としてキャリア決済やDMMポイントを選択することもできます。

入力内容を確認し「登録する」ボタンを押します。

「はじめる」ボタンを押します。これでDMM TVの登録が完了です。

DMM TV にログインした状態で、トップページからアカウントメニューを開きます。

メニューから「会員タイプ DMMプレミアム」を選択します。

ページをスクロールし、「DMMプレミアムを解約する」を押します。

ページをスクロールし、「解約手続きへ進む」ボタンを押します。

アンケートに回答し「次へ」ボタンを押します。

続きのアンケートに回答し「次へ」ボタンを押します。

続きのアンケートに回答し「アンケートを送信して次へ」ボタンを押します。

再び画面をスクロールし、「解約手続きを完了する」ボタンを押します。

これでDMM TVの解約が完了です。


Leminoで、『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』はレンタル配信中です。
| 月額料金 | 無料期間 | 見放題作品数 | ダウンロード | 同時再生可能端末数 | ポイント付与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1540円(税込) | 初回1ヶ月間無料 | 180,000以上 | 可能 | 4 | - |
Lemino トップページから、「会員登録」ボタンを押します。

「プレミアム会員登録」ボタンを押します。

dアカウントを持っている場合は「ログイン」ボタンを押します。そうでない場合は「dアカウント発行」に進みログインします。

キャリアがdocomo以外の場合は「ドコモのケータイ回線をお持ちでないお客さま」ボタンを押します。

dアカウントIDを入力し、「次へ」ボタンを押します。

dアカウントのパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

電話番号に届いたセキュリティコードを入力し、「次へ」ボタンを押します。

クレジットカードの情報を入力し、「確認画面へ」ボタンを押します。

「上記の利用規約/注意事項/パーソナルデータの取扱いに同意する」にチェックし、「申込内容を確認する」ボタンを押します。

「申込みを完了する」ボタンを押します。

これで Leminoの登録が完了です。

Leminoにログインした状態で、「設定」を開きます。

「dアカウント」(自分のメールアドレス)を押します。

「Leminoプレミアムの解約」を押します。

「解約手続きに進む」ボタンを押します。

現在契約中の主なサービス内にある、「Leminoプレミアム」の右にある「解約する」ボタンを押します。

「次へ(NEXT)」ボタンを押します。

dアカウントIDを入力し、「次へ」ボタンを押します。

パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

電話番号に届いたセキュリティコードを入力し、「次へ」ボタンを押します。

注意事項の「Leminoプレミアム 注意事項」ボタンを押します。

スクロールし「閉じる」ボタンを押します。

「Leminoプレミアムを解約する」と「Leminoプレミアムの注意事項に同意する」にチェックし、「次へ」ボタンを押します。

「次へ」ボタンを押します。

「手続きを完了する」ボタンを押します。

これで Leminoの解約が完了です。


J:COM STREAMで、『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』はレンタル配信中です。
| 月額料金 | 無料期間 | 見放題作品数 | ダウンロード | 同時再生可能端末数 | ポイント付与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,100円(税込) | なし | 25,000作品以上 | 可能 | 1端末 | - |
トップページ左上のメニューから「アカウント」「ログイン」を押します。

ページ下部の「J:COM STREAM サービス内容のご案内・お申し込み」を押します。

ページ中央部の「J:COMサービスをご利用でない方」を押します。

メールアドレスを入力して「お申し込み」を押します。

名前、生年月日、電話番号、パスワードを入力し「上記内容に同意する」をチェックし「次に進む」を押します。

SMSで届いた6桁のコードを入力し「次に進む」を押します。

クレジットカード情報を入力し「確認画面へ進む」を押します。

登録内容を確認し「この内容で登録する」を押します。

登録内容を確認しページ下部の「この内容で申し込む」を押します。

トップページ左上のメニューから「よくあるご質問」を押します。

『「J:COM STREAM」の解約方法を教えてください。』をタップし「詳しく見る」を押します。

「オプションチャンネル 解約」を押します。

ページ中央部の「マイページで手続きする」を押します。

「ログイン」を押します。

「テレビ・ネット動画」を押します。

「解約する」を押します。

「ログイン」を押します。

「同意する」を押します。

解約手続き内容を確認し、「同意する」をチェックし「申込内容確認へ」を押します。

ページ下部「この内容で申し込む」を押します。

©︎RKB