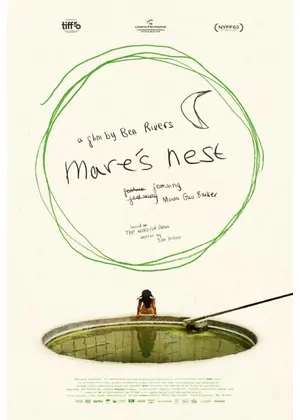
ルーマニア、ブカレスト。名門校の教師であるエミは、コロナ禍の街をさまよい歩いていた。夫とのプライベートセックスビデオが、意図せずパソコンよりネットに流失。生徒や親の目に触れることとなり、保…
>>続きを読むバルセロナ大学哲学科。イタリア人のラファエレ・ピント教授が、ダンテ「神曲」における女神の役割を皮切りに、文学、詩、そして現実社会における「女神論」を講義する。社会人の受講生たちも積極的に参…
>>続きを読む山に近い小さな町。女子高校生・まちは、女友達と短い物語を作り、それをリレーして遊ぶことを思いつく。次々と、紡がれる物語は、未来へと向かう夢。町に住む大人たちにも物語はあるが、それらは過去。…
>>続きを読む第76回カンヌ国際映画祭「監督週間 」正式出品 ロシア南⻄部の辺境、乾いた風が吹きつけるコーカサスの険しい山道。無愛想な目をした16歳の娘と寡黙な父親。二人は移動映画館で野外上映をし、ポル…
>>続きを読むある植物園、ふたりの少女が互いに宿命を解析しようとする。(『アリアとマリア』)とある男女が、キャンピングカーで旅に出る。(『Blue Through』)監督からの手紙を基に、大森靖子が楽曲…
>>続きを読む